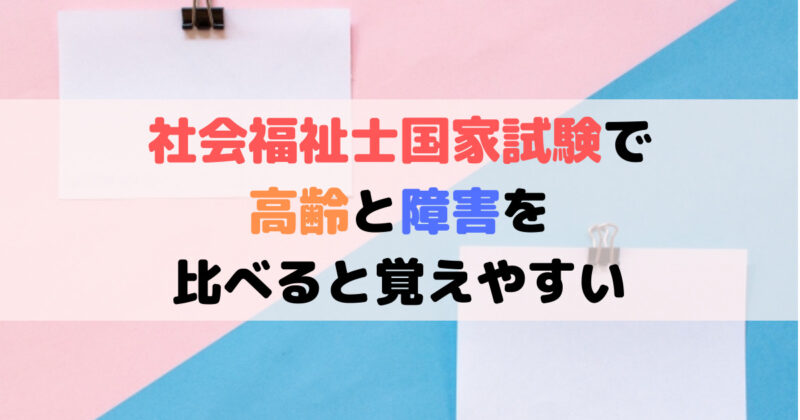この記事は働きながら社会福祉士の試験を受験する人におすすめです。
社会福祉士国家試験では自分が仕事をしている分野では高得点がとれます。勉強しなくてもある程度、高得点がとれます。
私はケアマネだったので「高齢者に対する支援と介護保険制」」の分野はほぼノータッチでした。
福祉の分野で働いている人は高齢、障害、児童等に分けれらるが高齢と障害は似たような制度になっています。
だから高齢分野と障害分野を比べると覚えやすいことに気づきました。
介護保険と障害福祉サービスとの比較
| 高齢分野の根拠法 | 障害分野の根拠法 |
|
老人福祉法 (高齢分野で憲法みたいな感じ) |
障害者基本法 (障害分野で憲法みたいな感じ) |
|
介護保険法(サービスの法律) |
障害者総合支援法(サービスの法律) |
2000年に介護保険制度が始まり、措置から契約へと介護保険サービスが導入されて3年後、障害の分野でも支援費制度といった措置から契約へサービス導入のため支援費制度が開始されました。
それによって、介護保険サービスと支援費制度のサービスが似ていたり、名前が違うが同じサービスがあります。
負担割合について
| 負担割合(自己負担)について | |
| 介護保険(高齢者) | 1割~3割(応益負担) |
| 支援費制度(障害者 | 負担能力に応じた費用徴収(応能負担) |
・応益負担とはサービスを使った分だけお金を払うこと。1回当たりの費用
・応能負担は何回サービスを使っても料金は一定
サービスの名前の違い
| 介護保険サービス | 障害の支援費制度サービス |
| 訪問介護(ホームヘルプ) |
居宅介護(ホームヘルプ) |
| 通所介護(デイサービス) |
生活介護(デイサービス) |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
共同生活援助(グループホーム) |
介護と障害で名前が全然違うので戸惑います。高齢分野の人からいうと居宅介護といわれると居宅介護支援事業所?(ケアマネ事業所)と思ってしまうことに注意が必要。
生活介護という言葉もケアマネをしている人だと訪問介護の生活援助と身体介護のという言葉に似ているため間違えやすいです。障害のグループホームは認知症以外の人を対象にしています。
介護保険と障害福祉サービスの独自サービス
|
介護保険独自サービス |
障害福祉独自サービス |
|
訪問看護 訪問リハビリ 福祉用具貸与 介護保険施設 認知症対応型共同生活介護 |
自立訓練 自立生活援助 就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援 同行援護・行動援護 共同生活援助 |
介護保険では介護を目的としていて、障害では自立や就労といったサービスが独自にあることがわかります。
尚、障害の自立訓練や自立生活援助の同等の介護保険サービスとして高齢者が病院から退院してきた際はケアマネや包括支援センターがその役割をに担っています。
障害の同行援護と行動援護は介護保険で見守り的なサービスになりますが、介護保険で見守りでサービスとして料金を取れるサービスはありません。
間違えそうな事業の名前
| 地域支援事業(介護保険) | 地域生活支援事業(障害) |
|
主に包括支援センターが行う仕事が必須事業になってます。(介護予防事業、包括的支援事業)任意事業もあります。 |
理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、手話奉仕員養成研修事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業 |
|
成年後見制度利用促進事業(任意事業) |
成年後見制度利用支援事業(必須事業) |
それぞれの事業に必須事業と任意事業があって内容は市区町村によって多少違いがあります。似たような制度で
・地域支援事業(高齢)では成年後見制度利用促進事業は任意事業
・地域生活支援事業(障害)では成年後見制度利用支援事業は必須事業
ややこしいわ!!この名前つけたやつはセンスないよ
また介護予防・日常生活支援総合事業というのも高齢分野にはあります。
介護と障害の同じような内容
介護保険と障害福祉サービスに同じような内容があります。完全一致ではないですが覚えやすいのでまとめました。
| 介護保険 |
障害福祉サービス |
|
要介護度(7段階) 要支援1~2、要介護1~5で要介護5が一番介護を必要とします。 |
障害支援区分(6段階) 区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが高いです。 |
|
介護支援専門員(ケアマネ) 1人当たりの担当件数が決まっています。実務経験5年と資格試験を合格する必要があります。 |
相談支援専門員 1人当たりの担当件数は決まっていません。実務経験5年と相談支援従事者(初任者)研修終了しないといけません。 |
|
ケアプラン 介護保険ではほぼケアマネジャーが作成 |
サービス等利用計画書 障害では自己作成が多く見られる |
|
地域包括支援センター 居宅介護支援事業所との連携や病院や施設から自宅への移行、困難事例や虐待対応など |
基幹相談支援センター 特定相談支援事業所との連携や病院や施設からの地域への移行や定着支援、困難事例など |
|
居宅介護支援事業所 ケアマネージャーが所属。ケアプランの作成・定期的なモニタリング |
特定相談支援事業所 相談支援専門員が所属。ケアプランの作成・定期的なモニタリング |
まとめ
「障害者に対する支援と障害自立支援制度」の分野は7問、「高齢者に対する支援と介護保険制度」の分野は10問です。
高齢分野で受験をした方が点数の配分上、若干有利な気もします。私はケアマネでしたので障害の分野が障害の分野が苦手でかなり時間を割きました。
だって障害の分野って身体障害者福祉法やら知的障害者福祉法やら精神保健福祉法やら発達障害者支援法やら法律がやたらと多くて難しいんだもん!!障害難しい!!
今回は以上でーす。